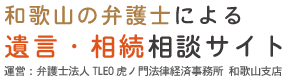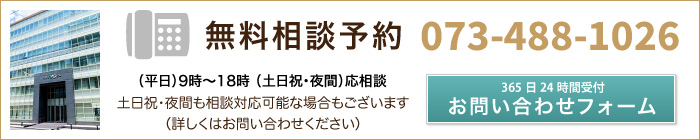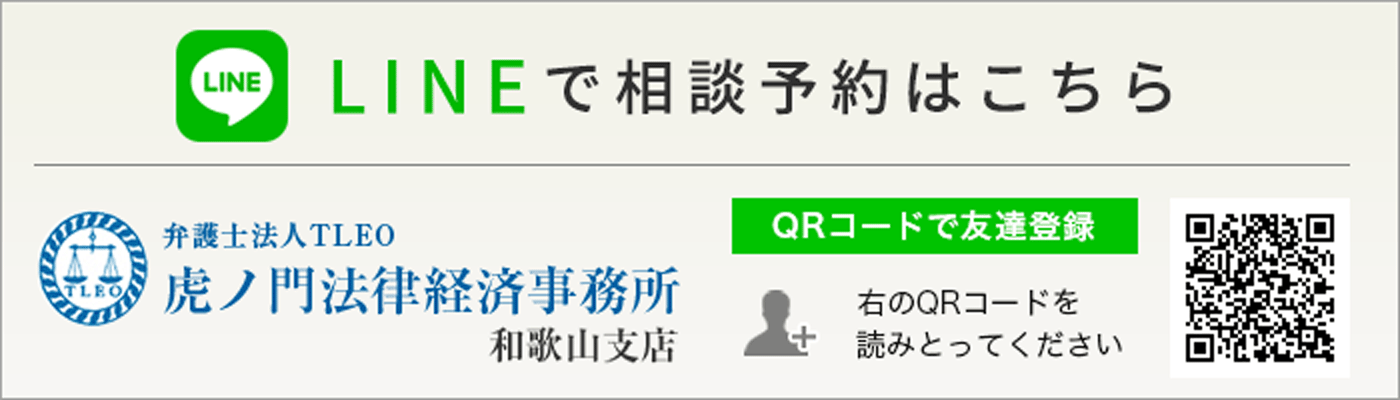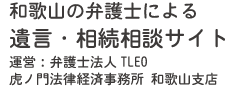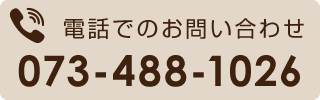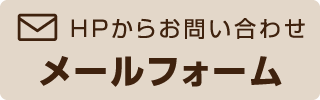はじめに
相続問題において、法定相続人がいない場合、特別縁故者への財産分与が検討されます。本コラムでは、内縁の妻が特別縁故者として認められ、全財産の分与に成功した事例を紹介します。この事例を通じて、内縁関係である方の、特別縁故者としての認定と財産分与の可能性について、具体的に解説していきます。
事案の概要
被相続人と依頼者の関係
被相続人Zと依頼者Aは内縁関係にありました。二人は法律上の婚姻関係にはありませんでしたが、長年にわたり夫婦同然の生活を送っていました。
相続人不在の状況
Zには子や兄弟姉妹がおらず、両親もすでに亡くなっていました。そのため、法定相続人が不在の状態となっていました。このような状況下で、、Aは特別縁故者としてZの遺産分与を求めました。
特別縁故者としての主張内容
長期にわたる同居の事実
Aは、Zが亡くなる26年前から、Zと同じ住所に居住していました。この事実は住民票によって証明されました。長期にわたる同居は、二人の関係の安定性と継続性を示す重要なものであるとと主張しました。
経済的一体性の証明
AとZが同居していたマンションは、二人の共有持分となっていました。また、Z名義の通帳からは、保険料、光熱費、新聞代など、両名の日常生活費用が引き落とされていました。これらの事実は、二人の経済的一体性を示すものであると主張ました。
家族としての関係性
Zは、Aの前の夫との子の結婚式にAと共に出席し、両家の挨拶では両親として挨拶をしていました。また、Aの前の夫との子の家族と一緒に家族旅行に行った写真も提出しました。これらの事実は、ZがAの家族の一員として受け入れられていたことを示していると主張しました。
パスポートの記載内容
Zのパスポートの「事故の場合の連絡先」にはAの氏名が、「本人との関係」には「内縁(の妻)」と記載されていました。これは、二人の関係性を示す重要な証拠であると主張しました。
写真等による生活実態の証明
Aは、交際開始時期の30年前から現在までの旅行の写真を提出しました。これらの写真で、長年にわたる二人の親密な関係を視覚的に証明しました。
相続財産管理人の意見(結果)
生計同一性の認定
相続財産管理人は、Z名義の通帳から両名の日常生活費用が引き落とされていた事実から、経済的一体性を認めました。また、Aの息子夫婦からの仕送りがZ名義の口座へ振り込まれていた点も、生計同一性を裏付ける事実として評価されました。
特別な縁故の認定理由
相続財産管理人は、長期にわたる同居、経済的一体性、家族としての関係性、そしてZがAの子らとも父親同様に接していた事実を総合的に評価しました。
その結果、Aは「被相続人と生計を同じくしていた者」ないし「その他被相続人と特別の縁故があった者」に該当すると判断され、裁判所も「申立人に対し、被相続人の別紙財産目録記載の相続財産全部を分与する。」と審判しました。
特別縁故者への分与を成功させるポイント
生活費支出の明確化の重要性
本件では、AはZと生計を同じくしていたため、Zが亡くなった後の生活費をZの口座から支出していました。しかし、相続財産管理人選任申立時には、その内訳を明らかにする必要がありました。そのため、日頃から家計簿等で支出の内訳をメモしておくことをおすすめします。
日常生活の証拠収集
本件では、長年にわたる旅行の写真や家族との交流を示す写真が重要な証拠となりました。特別縁故者としての認定を求める可能性がある場合、日常生活や家族との交流を示す写真や記録を意識的に残しておくことが有効です。また、公的書類での関係性の記載(本件ではパスポート)も重要な証拠となり得るので、可能な範囲でそのような記載を残すことも検討すべきでしょう。
まとめ
本事例では、内縁の妻が特別縁故者として認められ、被相続人の全財産の分与に成功しました。この成功の鍵となったのは、長期にわたる同居の事実、経済的一体性、家族としての関係性を示す具体的な証拠の提示でした。特に、日常生活の写真や公的書類での関係性の記載が重要な証拠となりました。
内縁関係にある方が特別縁故者として認められるためには、日頃からの証拠収集と生活費支出の明確化が重要です。家計簿の記録、共同生活を示す写真の保存、関係性が記載された書類など、計画的な準備が求められます。
法定相続人がおらず、内縁関係にある方の相続問題でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。
関連ページ

和歌山で遺言・相続のご相談なら虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へ
私たちは、和歌山県全域で、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄など、あらゆる相続問題に対応する法律事務所です。
「相続トラブルで家族と揉めている」「何から手をつけていいか分からない」「弁護士費用が心配」そんなお悩みをお持ちではありませんか?
当事務所は、全国ネットワークを活かした豊富な実績と最新のノウハウが強みです。
弁護士法人ならではの継続的なサポートに加え、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な手続きもワンストップで解決に導きます。
私たちは「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いを胸に、初回1時間の無料相談では、じっくりお話を伺うカウンセリングを重視しています。
費用についても明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。
大切な方の想いを未来へ繋ぐために、私たち経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。