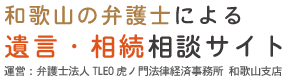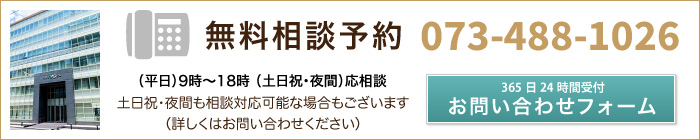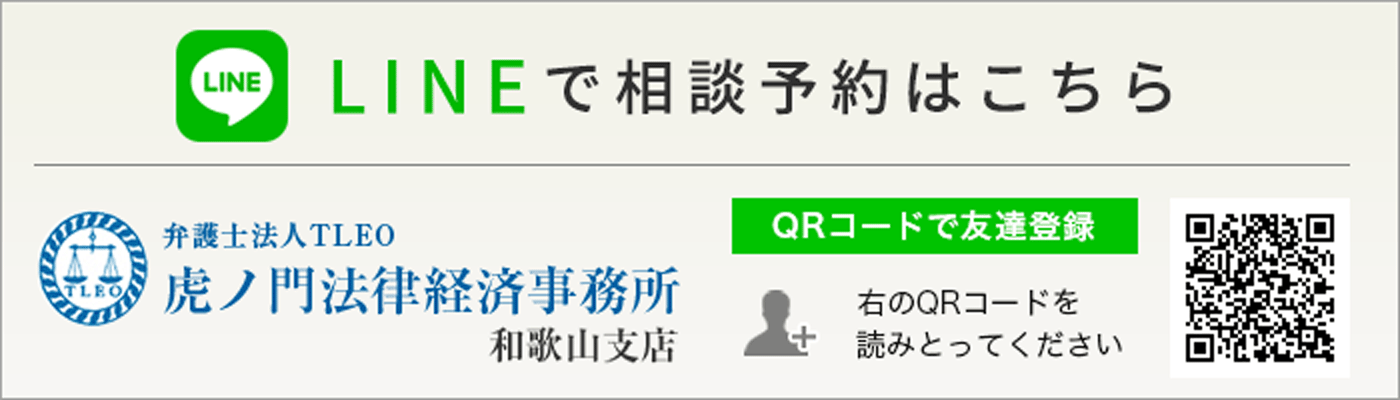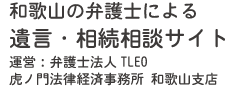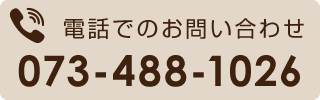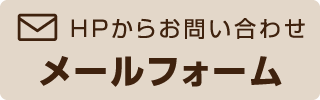相続放棄とは?期限を過ぎても認められる可能性
相続放棄とは、相続人が相続人としての地位を放棄し、初めから相続人ではなかったものとする制度です(民法第939条など)。しかし、この相続放棄には法定期間があり、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています(民法第915条)。そのため、期限を過ぎてしまうと相続放棄ができないのではないかと不安に感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、期限を過ぎても相続放棄が認められた特別なケースについて詳しく説明します。
相続放棄の基本的な期限について
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期間は「熟慮期間」とも呼ばれ、相続人が被相続人の財産状況を確認し、相続するか放棄するかを判断するための期間です。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなります。ただし、ここで重要なのは、いつの時点を「相続の開始があったことを知った時」とするかという点です。この起算点について、最高裁判所は以下のように示しています。
| 【最高裁判所第二小法廷・昭和59年4月27日判決《反対意見より抜粋》】 民法九一五条一項所定の「自己のために相続の開始があつたことを知つた時」とは、相続人が相続の原因事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を覚知した時をいうものと解するのが相当であり(大審院大正一五年(ク)第七二一号同年八月三日第二民事部決定・民集五巻一〇号六七九頁参照) |
期限を過ぎても認められる可能性がある場合とは
実は、相続放棄の期限には例外的な解釈が認められる場合があります。特に重要なのが、最高裁判所(第二小法廷・昭和59年4月27日)が示した「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」という基準です。つまり、被相続人の死亡を知っていても、相続財産の存在を知らなかった場合や、知ることが期待できない特別な事情がある場合には、期限の起算点が異なる可能性があるのです。
実際に認められたケース①:死亡を1年後に知った事例
死亡を知った時期への疑問
このケースでは、依頼者の父が死亡してから約1年後に、突然、固定資産税に関する通知が役所から郵便で届いたことがきっかけでした。一般的に、実子が親の死亡を1年も経過してから知ることは不自然と考えられ、相続放棄の申述が認められないのではないかという懸念がありました。
絶縁状態による正当な理由の説明
依頼者は被相続人(父親)と絶縁状態にありました。そのため、申立書の別紙として、被相続人及び親族との関係が途絶えていたことなどを詳細に記載して提出しました。これにより、死亡の事実を知るまでに時間がかかった正当な理由を説明することができました。
裁判所からの追加説明要求と結果
裁判所は、当初の申立内容だけでは判断が難しいと考え、絶縁に至った具体的な経緯についてより詳細な説明を求めてきました。そこで、家族関係が途絶えるに至った具体的な出来事や、その後の接触状況などについて、時系列に沿って詳しい補充説明を行いました。その結果、相続放棄の申述が無事に受理されました。
実際に認められたケース②:債務を4年後に知った事例
相続開始を知った時期の考え方
このケースの依頼者は、母親の葬儀に参列しており、死亡の事実は死亡時から知っていました。しかし、母親の死亡から約4年後になって、突然、債権者から問い合わせを受けたことで、相続財産の存在を初めて知ることとなりました。このような場合、通常であれば、熟慮期間の3ヶ月を過ぎているので相続放棄が認められません。そこで、この問題を解決するためには、相続放棄の期限の起算点をどのように考えるべきかが重要となります。
相続財産の認識に関する判例
先程もご紹介したとおり、最高裁判所は例外的な基準として「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」という判断を示しています。そこで、本件では依頼者が相続財産が全く存在しないと信じていたことを主張し、相続放棄の申述を行うことにしました。
相続放棄が認められた具体的な理由
被相続人との関係が希薄であったため、被相続人の生活状況を全く把握できていなかったこと、そして、債権者からの問い合わせが死亡から4年も経過してからのものであったことから、相続財産が存在しないと信じたことには相当の理由があると認められるべきであることを申立書の別紙に詳細に記載し、裁判所も相当性を認め、無事に相続放棄の申述が受理されることとなりました。
相続放棄の申述が認められるためのポイント
期限を過ぎた場合の主張の組み立て方
期限を過ぎた相続放棄の申述が認められるためには、以下の点に注意して主張を組み立てる必要があります。まず、被相続人との関係性や接触状況について、具体的な事実を時系列で整理することが重要です。また、相続財産の存在を知らなかったことについて、単なる怠慢ではなく、正当な理由があったことを具体的に説明できるようにしておく必要があります。
相続放棄申述の受理までの一般的な流れ
相続放棄の申述は、基本的に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申述に際しては、申述書のほか、戸籍謄本などの必要書類を提出する必要があります。また、期限を過ぎている場合には、上記のような特別な事情を説明する別紙を添付することが重要です。
まとめ
相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に申述する必要がありますが、特別な事情がある場合には期限を過ぎても認められる可能性があります。被相続人との関係や財産の認識状況を詳細に説明し、適切な証拠を添えることが重要です。相続放棄の期限に関するご不明点や特別な事情がある方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。
関連ページ

和歌山で遺言・相続のご相談なら虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へ
私たちは、和歌山県全域で、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄など、あらゆる相続問題に対応する法律事務所です。
「相続トラブルで家族と揉めている」「何から手をつけていいか分からない」「弁護士費用が心配」そんなお悩みをお持ちではありませんか?
当事務所は、全国ネットワークを活かした豊富な実績と最新のノウハウが強みです。
弁護士法人ならではの継続的なサポートに加え、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な手続きもワンストップで解決に導きます。
私たちは「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いを胸に、初回1時間の無料相談では、じっくりお話を伺うカウンセリングを重視しています。
費用についても明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。
大切な方の想いを未来へ繋ぐために、私たち経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。