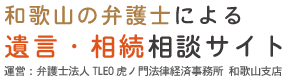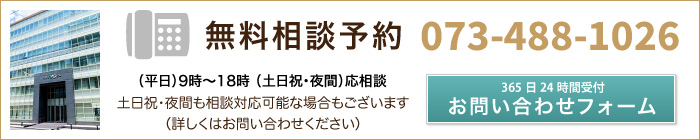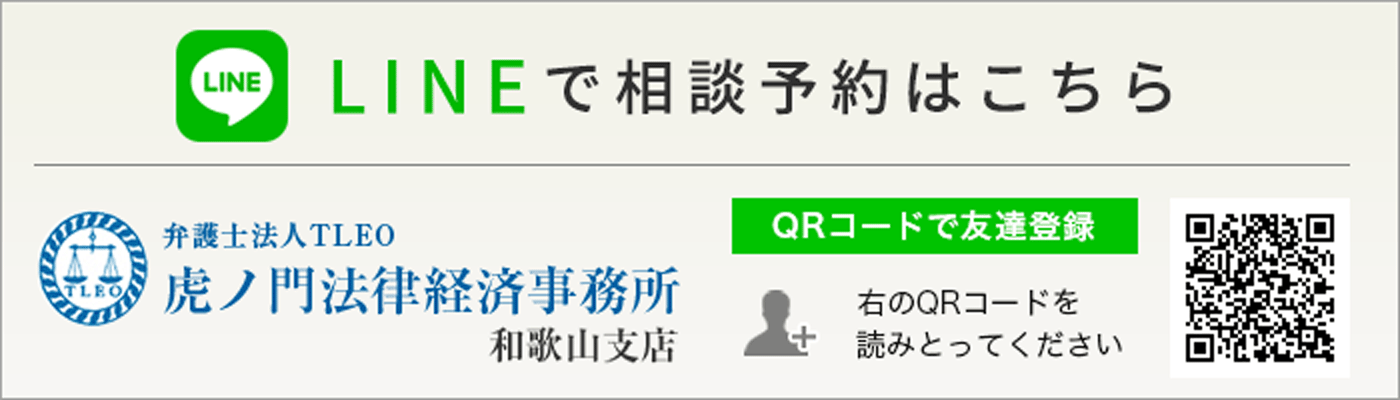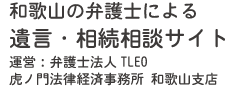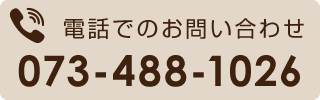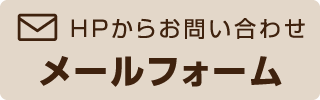はじめに
前回のコラムでは、特別縁故者への財産分与の事例として、被相続人の甥姪の子に対して相続財産の100%が分与された事案をご紹介しました。今回は、当事務所で扱った別の特別縁故者への財産分与の事案をご紹介します。具体的には、被相続人のいとこに対して相続財産の全てが分与された事例です。この事例を通じて、特別縁故者として認められるために必要な事情や効果的な主張方法について、詳しくご説明していきます。
事案の概要
被相続人と依頼者の関係
被相続人Zと依頼者Aはいとこ同士であり、幼少期から親密な関係にありました。Zは未婚で子供がおらず、兄弟姉妹もいませんでした。Zの両親もすでに他界しており、近しい親族はAのみで、AはZにとって重要な親族として多くの支援を行ってきました。
相続人不在の状況
Zには法定相続人がおらず、相続人不在の状態となっていました。Zには叔父叔母がいましたが、Aの父親以外は遠方に住んでいるなどの理由で疎遠になっていました。さらに、Zの家族背景として、5歳の時に両親が離婚し、14歳の時には親権者だった父親が亡くなりました。その後、Zは母親のもとへは行かず、父親の再婚相手が未成年後見人となりましたが、養子縁組はしませんでした。そのため、Zにとって身近な親族はAとその両親のみという状況でした。このような状況下で、AはZの遺産を受け取るために、特別縁故者への財産分与の申立てを行いました。
特別縁故者としての主張内容
幼少期からの深い付き合い
Aは、Zの幼少期から近所に住んでおり、お互いの家を頻繁に行き来する仲でした。二人は実の兄妹のような関係で、一緒に実家に帰省したり、日常の些細な相談をし合ったりしていました。AはZを結婚式に招待し、離婚後もZはAの子供の七五三に同行するなど、家族同然の付き合いを続けていました。また、Zは様々な契約書等で、緊急連絡先としてAの名前を記入していました。
無償での住環境維持
Aは、転勤の多かったZの依頼を受けて、1時間程度離れた場所にあるZの自宅を頻繁に訪れ、無償で清掃や住環境の維持に努めていました。この行為は、ZをAが実の兄のように思っていたからこそ自然に行えたものであると主張しました。
入院・医療対応への関与
Zが入院した際、AはZに最良の医療を受けさせたいという思いから、専門医のいる病院への転院の手続きを一人で行いました。病院のカルテには、Aが継続的にZを見舞い、病状説明に立ち会い、医師と密に連絡を取っていた記録が残されていました。また、手術の同意書や退院支援計画書にもAの名前が記載されていました。
財産管理の一任
Zは、Aに預金通帳、キャッシュカード、パスポート、家や車の鍵、パソコン、資産関係の書類等一式を託し、全ての資産をAに遺贈したい旨を伝えていました。Aは、Zの療養看護だけでなく、財産管理も一貫して行っていました。特筆すべきは、Aが自己の資金を用いて、Zの生前の意思に従い、診療費、光熱費、税金、管理費等の全てを支払っていたことです。これらの支払いに際し、Aは被相続人Zの預貯金には一切手をつけておらず、全て自己負担で行っていました。このような行為は、Aが家族の債務を支払うのは当然だという感覚を持っていたからこそ可能だったと主張しました。
葬儀の執行と墓の祭祀継承
Zの死後、Aは喪主となり、葬儀および法事の進行を一人で行いました。また、Zから墓の権利書と毎年の支払いを託されていたため、Aは墓を承継し、使用料の支払いを継続していました。
その他の妥当性を示す状況
Zは生命保険の受取人を一貫してAに指定し、更新の度にそのことをAに伝えていました。また、全ての資産に関する書類をAに渡し、遺贈の意思表示をしていました。これらの事実から、ZはAが当然に相続するものと考えていたと推測されると主張しました。
相続財産管理人の意見(結果)
特別縁故関係の該当性
相続財産管理人は、AとZの関係について、単なる親族関係にとどまらない「特別の縁故があった者」であると認めることが相当だと判断しました。その理由として、Zの体調を気遣い頻繁に連絡を取り合っていたこと、専門医の診察を受けられるよう尽力したこと、Zが終末期の看護をAに任せていたこと、そしてAがZの死亡届提出等の手続きや葬儀等の祭祀を行ったことなどが挙げられました。
分与の相当性
相続財産管理人は、Aが被相続人の診療費、公共料金及び税金の支払いや、財産関係その他重要書類等の保管など、被相続人のために一定の死後事務を行っていたことから、Aに被相続人の財産を分与することが相当であると判断しました。
分与の内容と程度
相続財産管理人は、諸般の事情を考慮した結果、相続財産管理人の報酬を除く全ての相続財産をAに分与することが、被相続人の意思に合致すると認めました。その理由として、Zが遺言書を作成する時間的・体力的余裕がなかったと考えられること、財産関係その他重要書類等をAが保管していたこと、死亡保険金の受取人にAが指定されていたこと、Zの生い立ちや生活歴等からA以外に相続財産の分与を受けるべき者がいるとは考えられないことなどが挙げられました。
特別縁故者への分与を成功させるポイント
特別縁故者として財産分与を成功させるためには、被相続人との関係を詳細に立証することが重要です。特に、次のポイントを押さえ、具体的な事実と証拠を丁寧に積み上げることで、特別縁故者としての地位を認められる可能性が高まります。
- 長期にわたる深い関係性の証明
幼少期からの交流や日常的な関わりを具体的に示すことが重要です。 - 無償の支援の実績
住環境の維持や財産管理など、金銭的見返りを求めない支援を行っていたことを示すことが重要です。 - 医療や介護への積極的な関与
入院時の対応や医療関係者とのやり取りなど、被相続人の健康に関する深い関与を示すことが重要です。 - 財産管理の一任
被相続人から財産管理を任されていたことを示す具体的な証拠を示すことが重要です。 - 葬儀や祭祀の継承
被相続人の死後の対応や墓の継承など、家族同然の責任を果たしていたことを示すことが重要です。 - 被相続人の意思の推定
生命保険の受取人指定や資産関係書類の引き渡しなど、被相続人の意思を推定できる事実を示すことが重要です。 - 第三者の証言
医療関係者や近隣住民など、第三者からの証言や記録を活用することが重要です。 - 一貫した関与の証明
単発的でなく、長期にわたって一貫した関与があったことを示すことが重要です。
まとめ
本コラムでは、特別縁故者への財産分与の成功例として、被相続人のいとこに対して相続財産の全てが分与された事例を紹介しました。この事例から、特別縁故者として認められるためには、被相続人との長期にわたる深い関係性、無償の支援、医療や介護への積極的な関与、財産管理の一任、葬儀や祭祀の継承など、具体的な事実と証拠を丁寧に積み上げることが重要であることがわかります。また、被相続人の意思を推定できる事実や第三者の証言も有効です。
前回のコラムで紹介した甥姪の子への分与事例と照らし合わせてみると、以下のような共通点が浮かび上がります。
- 被相続人との長期にわたる深い関係性の証明
- 療養看護や財産管理など、具体的な支援の実績
- 被相続人の意思を尊重した行動(葬儀の執行など)
- 相続財産の維持管理への貢献
特別縁故者への財産分与は、法定相続人がいない場合の重要な選択肢ですが、その申立ては複雑で専門的な知識を要します。そのため、経験豊富な弁護士のサポートを受けることが成功への近道となります。相続問題でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますので、お気軽に当事務所までご相談ください。
関連ページ

和歌山で遺言・相続のご相談なら虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へ
私たちは、和歌山県全域で、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄など、あらゆる相続問題に対応する法律事務所です。
「相続トラブルで家族と揉めている」「何から手をつけていいか分からない」「弁護士費用が心配」そんなお悩みをお持ちではありませんか?
当事務所は、全国ネットワークを活かした豊富な実績と最新のノウハウが強みです。
弁護士法人ならではの継続的なサポートに加え、税理士や司法書士などの専門家と連携し、複雑な手続きもワンストップで解決に導きます。
私たちは「相続問題で悩む人を少しでも減らしたい」という想いを胸に、初回1時間の無料相談では、じっくりお話を伺うカウンセリングを重視しています。
費用についても明朗な料金体系で、安心してご依頼いただけます。
大切な方の想いを未来へ繋ぐために、私たち経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。